北に逃げて感じ入る
親の介護だけでなく、新しい仕事を立ち上げようとした矢先に病気が判明し、気持ちの焦りやらストレスやらでどうに気持ちの整理がつかなくなり、演歌ではないけれど「北」を目指して車をひた走らせた。

「北に行く」という言葉には「逃げる」という意味も含まれているらしい…
まあ、にっちもさっちも行かない現実に逃げたくなった気持ちも嘘ではない…。

雨樋の中を流されるような高速道路を走るのも嫌なので、下道ばかりを走って福島県に入ったのは家を出て二日目のこと。
相馬市の海岸線に出ると夏草の生い茂っただだっ広い空き地の中に「震災遺構」が見えてくる。
ここに生活の営みがあったことを示すものはなにもない。
廃墟となった「中浜小学校」とお寺があったことを示す石碑が立っている。

立派な道ができ家々は内陸に移りはしたものの、あれから13年経ったというのにここだけは時が止まったかのようだ。
さらに車を進めインバウンドの観光客らしき人並みでごった返す「ああ松島や…」の松島を通リすぎると「奇跡の一本松」で有名な「陸前高田」に到着する。

沿岸から内陸の数キロにわたり「震災遺構」や「津波伝承館」を除き人の営みを感じさせるものはない。
破壊された建物、モニュメントと化した一本松。
実際にこの目で見るまではその存在に懐疑的であった私だけれど、実際のモノを見て感じるものは伝承では伝わらない圧倒的な迫力があり感情を揺さぶられる。

人の代が変わり徐々に災禍の記憶が薄れているのは仕方ない。でも、「実際にここでこんな事がありました」と、眼の前に圧倒的な現実を見せることの意義はとてつもなく大きい。
懐疑的であった自分の考えは「よそ者の不見識」だと気づき恥入った。

しかし、その後にまわった、まるで売れ残り続出の住宅造成地のような風通しの良すぎる陸前高田の嵩上げされた市街地の現実をみると、真の意味での復興は人が住めなくなった土地に震災遺構を残すことでも大規模な造成をして安全な街を作ろうとするだけでは進まないことに気付かされた。

あれから13年。
場所によって震災の被害は様々なので一言ではくくれないことは重々承知の上だが、陸前高田に来る途中で立ち寄った塩竈市の水産物仲卸市場で元気に生活を営む人々の姿を見ると、真の意味での復興は地元の人達が自らの手で作り上げ時を進めていくものだと感じられた。

越前高田は行政主導で市街地の嵩上げ・住宅地の高台移転を選択した。
それはそれで安全な街を作ろうという意味においては間違いはない。
しかし、この選択は街や海、歴史など長年にわたり営まれてい人々の生活を地元の人から切り離してしまうこととなってしまった。
この街は時が止まってしまったかのようだ。
本来なら海岸沿いにあるカキ小屋…海から車で5分近く走った内陸にあるというのもなんだか現実を映し出している。

牡蠣は美味しかったけどね…。
この街のさらなる復興を願う。でも…難しいだろうなぁ…。
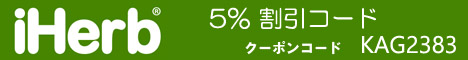
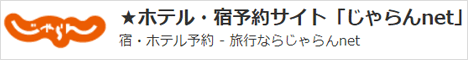
 Author:Chariketta
Author:Chariketta
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません